当院は行動目標1の「危険薬の誤投与防止」に取り組んでいる。その中のベストプラクティス16(NDP)の一つである “輸液ポンプ、シリンジポンプ(以下ポンプと略)の操作・運用・管理方法の標準化と教育”へのチャレンジについて紹介する。日本医療機能評価機構の年報によると、医療事故における医療機器が関連した割合は3.3%、ヒヤリハットの要因が医療機器である割合は1.1% と多くない。しかし、稀ではあるが医療機器が関連した死亡事故が報告されている。
輸液ポンプ、シリンジポンプについての取り組みと成果
琉球大学医学部附属病院 安全管理対策室 久田 友治、国吉 ひろみ、西巻 正
概要
当院は病床数600、病床稼働率83%、平均在院日数は17.5日 である。看護体制は2007年から7:1となり、臨床工学技士は12名である。2004年から2008年に報告された医療機器全体についてのインシデントは167件で、そのうちポンプのインシデントは42件、人工呼吸器は29件等であった。インシデントは各部署の端末からオンラインで報告される。患者への影響レベルは、国立大学医学部附属病院医療安全管理協議会の定義を用いた。
取り組み
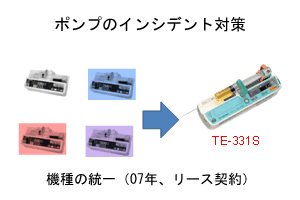 当院ではポンプのインシデント対策の一つとして、設定後10分以内に異なった医療者がリストに沿ってチェックを行っている。また、2007年にポンプの機種を変更して統一し、リース契約とした(図1)。ポンプの使用法についての研修は、毎年これまで主に看護師を対象に行ってきたが、2007年からの機種変更に伴い、研修医を含む職員を対象に各病棟で説明会を実施した。
当院ではポンプのインシデント対策の一つとして、設定後10分以内に異なった医療者がリストに沿ってチェックを行っている。また、2007年にポンプの機種を変更して統一し、リース契約とした(図1)。ポンプの使用法についての研修は、毎年これまで主に看護師を対象に行ってきたが、2007年からの機種変更に伴い、研修医を含む職員を対象に各病棟で説明会を実施した。
成果
年別の医療機器全体のインシデント報告件数は図2で示すように2004年の20件から、2008年50件へと増加した。一方、ポンプのインシデント報告件数は2004年の12件から減少傾向にある(図2)。その結果、ポンプのインシデント報告の医療機器全体に占める割合は減少傾向となった(図3)。インシデントの報告者を職種別にみると、看護師36件、医師5件、放射線技師1件であり、影響レベルは1が18件、2が19件、3aが5件であり、3bはなかった。
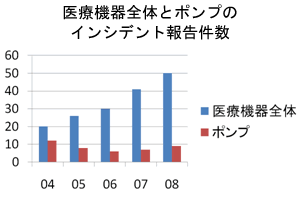
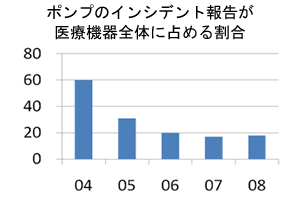
考察
1)医療機器全体のインシデント報告件数は増加しているが、影響レベルの大きい事例は少なく、積極的なインシデント報告を反映していることが示唆された。 2)ポンプの報告件数の増加はなく、むしろ全体に占める割合が減少傾向にあり、また、影響レベルの大きなインシデントがないことから、リスクマネジメントが一定の役割を果たしていることが示唆された。 3)ポンプのインシデント報告は続いており、今後もインシデントのフィードバックと使用方法の研修を継続することが必要だと考える。
(2010-4-3)