目標8[患者・市民の医療参加] Q&A
2010/06/02 追加
Q.「患者誤認防止」に関する質問です。当院では誤認防止のため、患者さんにバーコード付きネームバンド装着をしてもらっています。成人の場合は、特別なことがない限り装着されていますが、小児病棟では、点滴ルートの邪魔になるとか、皮膚がかぶれたことがあるとか、子どもが寝ている時に手首のネームバンドを探すのに起こしてしまい、ご家族から苦情が来る等の理由で、ネームバンド装着ができていません。今では、入院患者すべてネームバンド装着をしていない状況です(そのかわり、ネームはオーバーテーブルや患者さんの点滴スタンドに貼り付けています)。全国的に小児にネームバンドをつけているのか、それとも別の方法でやっているのか、参考になる情報がありましたらお願いします。
A.以下に、1大学病院、5公立病院、合わせて6病院にヒアリングした状況を示します。【装着の有無】1)6病院とも原則装着としている。ただし、アレルギー患者や一部装着不可能な場合は、他の方法をとっている。他の方法をとる場合に、その方法をマニュアルにしている病院も複数ある。 2)全員装着をどのくらい強く実施しようとしているかは病院によって差がある。誤薬などのリスクを感じている病院(子どもが違うベッドに移動していたなどのインシデントを経験した病院)では、親への説明を強化して、ほとんどの患者に装着している。【装着の推進、装着できない場合の各病院の工夫】1)小さいサイズのものを使用する(大きいと湾曲して読み取りにくいため) 2)アトピーなどの場合は症状の軽い場所に装着(足首など) 3)擦れたりかぶれたりしないように包帯で保護 4)マニュアルで、四肢装着不可能な場合は、カードケースにリストバンドを入れベッド柵につける 4)新生児の場合は、コットあるいはクベースに貼付することになっている 5)スキントラブルが発生する時は、リストバンドを点滴架台にぶら下げて使用している 6)マニュアルでは、装着困難な患者は、ネームバンドを2枚つなぎ、ベッドのヘッドボードにつける、衣服の紐やボタンホールにつけるとしている 7)リストバンド装着不可能と判断した場合は、着衣に名前を明記していただくことになっている 【家族の理解を得る工夫】1)入院時のオリエンテーションで、必要性についてリスクや他の方法では適当でない理由も含めて(子どもが自分でベッドを移動し誤薬など)説明し、必要性を理解していただき同意を得る 2)家族と一緒にリストバンドで点滴・内服・検査など確認する 3)認証の音量を最小に絞る、消音する(夜間の音への苦情に配慮)
※以上のヒアリング結果から、ご懸念のように、自分で名前の確認ができない小児こそ、リストバンドを活用することが重要と思われ、患者さんに装着という本来の使い方がされていないのは、患者誤認のリスクを高めることとなります。ご家族にも取り違え事例などリスクを含めてあらかじめ説明をしていただく工夫をお願いします。できれば現場スタッフと説明用のリーフレットを作成されることをお勧めします(作成プロセスでスタッフの認識を高める効果も期待できます)。ぜひ、原則は装着としていただき、どうしても装着できない場合の対応を別途検討するようにしていだけたらと思います。リストバンドがどこについているかわからず探すために子どもを起こしてしまうのであれば、どこにつけてあるかを示す図をベッドに貼っておくなどの工夫も考えられます。ベッドにリストバンドを貼り付けている患者では、例えば、放射線検査に行くなど、病室から離れる場合の確認方法なども決めていただく必要があります。
患者さんの確認について
Q.患者さんの誤認防止のために「患者さんに名前を言ってもらう」取り組みをしています。リストバンドを導入して照合させてもらっていますが、なおかつ「患者さんに名前を言ってもらう」ことには職員に抵抗感があるようです。「臨機応変に」ということにすると、いつまでも名乗ってもらえないのが現実だと実感しています。何かアドバイスをいただけますか?
A.ご質問から、貴院ではリストバンドを見せていただく、ということを実践されていると拝察され、なかなか実践できていない病院もあるので、すばらしいことだと思います。 患者さん誤認防止のために「患者さんに名前を言ってもらう」ことと、リストバンドを見せてもらうこととの二つの確認方法の役割、効果をどのように考えたらよいか、ということを考えてみたいと思います。
この問題について、他でも確立された知見が見当たらないので、以下、心理学的な検討と、各地の医療機関の情報をもとに、私見を述べます。ご参考になれば幸いです。 なお、リストバンドにバーコードがついていて、輸血や点滴に貼られたバーコードと照合するという場合は、リストバンドは患者確認ということだけではなくその血液や薬剤が今、ここですべきものかを確認し、また実施を記録する意味合いがありますので、別に考えることにして、ここでは、お名前が書かれたリストバンド、ということにして考えます。
お名前を患者さんに言っていただく、ということの一番重要な意味は、お名前が正確に確認できる、ということです。 医療者が患者さんの名前を言って患者さんがハイと返事をするのは、自分の名前が呼ばれると期待している患者さんが聞き違えて(あるいは十分聞き取れないのに)ハイと返事をする可能性が高いので危険なのはご承知の通りです。
一方、医療者がリストバンドの氏名を目視し、自分の持っている書類やラベルの名前と照合するのでは、医療者が見間違え、合っていると思い込んでしまう危険が少なからずあります(たとえば、類似名の薬剤の間違いを鑑査時に見逃すのと同じことです)。
心理学的には、目視だけで、つまり視覚情報だけで確認するよりも、声を出し聴覚も使って確認するほうが、意識水準が高まるとともに、複数のチャンネルを使って確認できるので正確性は高まります。チャンネルを多くするという意味では、医療者が声に出して読むことも効果的です(ただし、医療者の思い込みの読み違えは避けることができないので、そこに自分でフルネームの言える患者がいるのであれば言っていただくことが望ましいと考えられます)。
お名前を言っていただく二番目の意義は、患者さんに、患者確認、安全確保に参加している、という意識を持っていただくことです。それによって、お名前に限らず何かおかしいと思ったときに医療者に質問や指摘をしていただきやすくなります。
三番目として、お名前を自分で言うことを習慣化していただくという意味があります。外来で診察や検査を受けることになったときにはリストバンドを付けていませんから、基本的にお名前を言っていただくことを当たり前のことと思っていただく必要があります。
それではリストバンドとお名前を言っていただくことをどのように使ったらよいか、ということです。次は一案ですので、貴院のルールを作られるときの参考にしてください。
1.患者さんがお名前を言える状態のときは、お名前を言っていただくことを優先する(各地の病院のマニュアル等では、「お名前が言えないときにリストバンドで確認」となっているところもあります)。 ※リストバンドを見せてもらうことを誰にでも統一して行うのであれば、リストバンドによる確認とは別に「お名前をおっしゃってください」とお願いするのではなく、リストバンドを見せてもらいながら「では、ご一緒にリストバンドのお名前を読んで確認をお願いします」と呼びかけて名前を声に出して言ってもらう方法があると思います。患者さんのほうからすると、誰にでも統一してリストバンドを使用するという意味では、そのほうがわかりやすいかもしれません。
2.自分では言えない患者さん、意識が低下している患者さんなどでは、リストバンドを医療者が声に出して読んで確認する。
3.患者さんのおっしゃったお名前にあいまいなところがあるとき、あるいは、類似名の患者さんが同じ病棟にいたりして取り違えの危険が高いと考えられるとき、また、輸血のような特にリスクの高い行為を行うときは、名前を言っていただいたあとに、それに加えて「ありがとうございます。念のためにリストバンドを拝見させてください」と二重に確認することで正確性を高める。
いずれにしても、ぜひ場面ごとに、病院としての原則の確認方法と、もしそれができない場合はこうするという代替のやり方を検討して明文化していただければと思います(ルールを作るときに、現場で実践される方の意見をきいていただくと守りやすいルールとなります)。危惧されているように、「臨機応変」でやってしまうと、省略するほうに流れていきます。また医療者によって対応が違うのは患者に不信や不安を与えます。
また、職員は、患者さんから嫌がられる、患者さんから理解されない、ことが気になって実行できないようです。職員への啓発と同時に、患者さんへの働きかけを強化して名前を言うことの重要性を認識していただくことが重要と思われます。実践を続けている病院の例では、数年継続すると患者さん側がしっかり理解して、「名前を言うのは当たり前」とおっしゃるようになってきています。
Q.「患者と医療者の協同によるフルネーム確認」の評価方法について、人数や方法、時期など具体的な例を教えてください。
A.患者さんと医療者を対象にしたアンケートや聞き取り調査によって、評価を行うことができます。 栗原中央病院では、半年に1回程度、外来患者さんと入院患者さん、各50人ずつに聞き取り調査をしています。
外来患者さんへの聞き取り項目は、①フルネームを言っていただく病院の方針をポスターなどで知っていたか、②フルネーム確認することが決められている場面(外来診察時、採血時、放射線検査時、会計時)で、実際にフルネームを聞かれたか、③毎回確認をされることをどう思うか、などの項目です。
入院患者さんへの聞き取り項目は、①フルネームを言っていただくことについて看護師から説明があったか、②フルネーム確認することが決められている場面(注射・点滴時、採血時)で、実際にフルネームを聞かれたか、③毎回確認をされることをどう思うか、などの項目です。
また、医療者を対象にしたアンケートでも、どの程度、決められた方法で患者確認を実施しているかを尋ねています。他に、退院アンケートに患者確認に関する項目を入れることも考えられます。
Q.外来診療場面や理学療法室ではおなじみの患者さんが多いので、毎回の名前の確認について抵抗感があるのですが、どのような取り組みが効果的でしょうか?
A.患者さんに対して、「名前を聞くのは患者さんを知らないからではなく、知っていると思っても確認が必要なこと」を理解していただく必要があります。「患者さん確認は、安全のために病院の方針として行っているので協力してほしい」旨を、ポスターやリーフレット、ホームページ、入院案内等、さまざまな媒体を使って、何度も目につくように伝えることが重要です。ポスターは外来待合室や病棟だけでなく、診察室や検査室の入り口ドアなどにも貼って効果を挙げている病院があります。
名前を聞くときに「安全のために、お名前をおっしゃってください」と、その意図を付け加えることも有効です。取り組みを継続している病院では、入院患者さんでは50%以上、外来患者さんでも30%以上が「毎回名前を言うことは当たり前」という意識に変わってきています。
医療者にも抵抗感があるかもしれませんが、医療者自身も患者さんを知らないから名前を聞くのではないことをきちんと意識する必要があります。そして、外来診察などの場面で顔見知りのつもりで患者誤認が起こりそうになったインシデントや、病院内での同姓や類似名患者の多さなどを示しながら、必要性を認識してもらうことが重要と考えられます。
Q.パソコン画面上で患者さんの選択を間違えないためには、どのような対策がありますか?
A.「患者選択画面」で患者名のフォントの大きさや色(字と背景の色)、表示される位置などについて見やすいかどうか検討し、変更が可能な部分があれば改善すると、選択エラーを減らすことができます。
また、選択の際に画面を指差し、名前を読み上げて確認する(指差し呼称)ことが効果的と考えられます。パソコンをクリックして選択したあとに、画面で選択結果を確認することが忘れられがちですので、選択結果を見て「○○▲▲さん」と声に出す習慣をつけることも有効と考えられます。患者さんが同席している場面であれば、状況によっては患者さんにも画面を見ていただいたり、患者さんに聞こえる声で選択した名前を読み上げるとよいでしょう。
飯塚病院では、パソコンでオーダーしたあと、指示シールを印刷してカルテに指示として貼付しています。電子カルテになっていないためですが、このシールを印刷する間(4秒間)はパソコン画面一杯に「○○△△さんの指示を印刷しています」と表示されます。この対策をとる前は医師の患者さん間違えが月に2~4件ありましたが、これ以後は1件起こったのみです。下記は画面のイメージです。
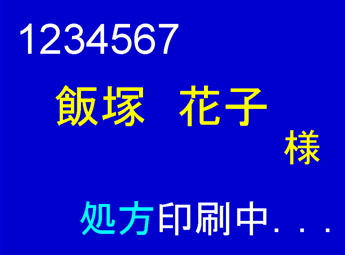
Q.院内患者図書室の本は、どのような種類の本が適切ですか?
A.患者図書室に必要な本の種類や選択の仕方については、共同行動ホームページにツールとして掲載している「患者図書室の設置と運営の指針」に詳しく記載していますので、ぜひご覧ください。また、具体的な選書については、日本図書館協会の健康情報委員会が中心となり作成した「公共図書館のための『健康情報の本』選定ノート」 URL http://booklog.jp/users/kenkojoho/ が役立ちます。
また、例えば東邦大学医学部附属病院の「からだとしょしつ」のホームページ
http://www.mnc.toho-u.ac.jp/mmc/karada/index.htmには同図書室の蔵書一覧が掲載されていますので、参考になると思います。
Q.「医療安全」ということを患者図書室の利用目的の視点ではどのようにとらえたらよいでしょうか?
A.患者さんが自分の病気や治療について理解を深めると、医療者の説明を理解しやすくなり質問もしやすくなります。それは、医療者と十分コミュニケーションをとって納得して治療を選択をすることや、治療の結果について適切な認識をすることなどにつながります。また、治療や薬剤の副作用などに患者さん自身が早く気づいて医療者に伝えやすくなる、患者さん自身が安全のために気をつけるべきことがわかる、万一医療者のエラーが起きたときにそれに気づく可能性が高まる、など事故防止の効果も期待できます。